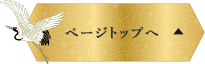日本の城と戦国武将
蜂屋頼隆(蜂屋頼隆と城一覧)

蜂屋頼隆(蜂屋頼隆と城一覧)/ホームメイト
「蜂屋頼隆」(はちやよりたか)は、戦国時代~1589年(天正17年)9月25日までを生きた戦国武将です。



![]()
- 小
- 中
- 大
「蜂屋頼隆」(はちやよりたか)は、1534年(天文3年)~1589年(天正17年)まで活躍した戦国武将です。1564年(永禄7年)から、「織田信長」の家臣として勢力拡大に貢献し、「浅井長政」(あざいながまさ)と「朝倉義景」(あさくらよしかげ)を討伐。それらの功績が認められ、「肥田城」(ひだじょう:滋賀県彦根市)城主となり、のちに「岸和田城」(きしわだじょう:大阪府岸和田市)に入城します。織田信長亡きあとは「羽柴秀吉」(のちの豊臣秀吉)に仕えて、「敦賀城」(つるがじょう:福井県敦賀市)の城主となりました。蜂屋頼隆は生涯で2度も城主に命じられる実力者であり、晩年には羽柴姓を授けられるなど、豊臣秀吉からも高い信頼を得た人物です。蜂屋頼隆の生涯と、ゆかりのある城についてご紹介します。