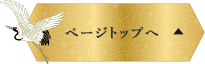日本の城と戦国武将
脇坂安治(脇坂安治と城一覧)

脇坂安治(脇坂安治と城一覧)/ホームメイト
「脇坂安治」(わきざかやすはる)は、1554年(天文23年)~1626年(寛永3年)8月6日までを生きた戦国武将です。



![]()
- 小
- 中
- 大
「脇坂安治」(わきざかやすはる)は、1554年(天文23年)から1626年(寛永3年)まで活躍した戦国武将です。「賤ヶ岳の戦い」(しずがたけのたたかい)で功績を挙げた7人の武将「賤ヶ岳の七本槍」(しずがたけのしちほんやり)のひとりとして知られています。そんな脇坂安治は「浅井長政」(あざいながまさ)に仕えたのち、「明智光秀」、「羽柴秀吉」(のちの「豊臣秀吉」)と主君を変え、「関ヶ原の戦い」では西軍から東軍へと寝返って「徳川家康」に付くなど、上手く立ち回り戦国の世を生き抜きました。また水軍としての活躍を活かして、海に近い立地に城を建築しています。脇坂安治の生涯と、ゆかりのある城について見ていきましょう。