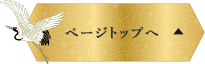二階堂行政がいつ頃生まれたのかは不明ですが、父は遠江国(現在の静岡県西部)の国司「工藤行遠」(くどうゆきとお)で、藤原南家(ふじわらなんけ)の家系です。
母は、「熱田神宮」(愛知県名古屋市熱田区)の大宮司「藤原季範」(ふじわらのすえのり)の妹だとされています。藤原季範には「由良御前」(ゆらごぜん)という娘がおり、この由良御前が源頼朝の母。二階堂行政から見ると由良御前は従姉妹で、源頼朝は従姉妹の子供にあたります。
二階堂行政はもともと下級貴族で、朝廷に仕える役人でした。1180年(治承4年)には「主計少允」(かずえのしょうじょう:会計部署の責任者)に就任しており、文官として優秀だったことが伺えます。
その後、源頼朝に召し上げられ、二階堂行政は鎌倉幕府の文官として従事することになりました。1184年(元暦元年)には公文所(くもんじょ:政務を司る役所)奉行へ就任。源頼朝に取り立てられた経緯には、お互いの母同士が親戚関係にあったことも少なからず関係していたと考えられています。
1191年(建久2年)、政所(まんどころ:財政や訴訟を司る行政機関)の開設に伴い、二階堂行政は初代政所別当(べっとう:長官)である「大江広元」(おおえのひろもと)に次ぐ役職に就任。
1193年(建久4年)には、二階堂行政も政所別当へ昇格しました。初代政所別当である大江広元は、朝廷との折衝などで不在にすることが多く、そのような場合に二階堂行政が実務の要となっていたと言われています。

1199年(建久10年・正治元年)、初代将軍の源頼朝がこの世を去ると、嫡男である源頼家が18歳という若さで2代将軍に就任しました。
しかし、まだ若い源頼家は盟主として未熟であり、自分勝手な政治判断を下そうとします。源頼家の独裁政治を防ぐため、有力な御家人(ごけにん:将軍と主従関係にある武士)達によって発足したのが、源頼家を複数人で指導する13人の合議制でした。
構成員は、「北条時政」(ほうじょうときまさ)、「北条義時」(ほうじょうよしとき)、大江広元、「中原親能」(なかはらのちかよし)、「三善康信」(みよしのやすのぶ)、「比企能員」(ひきよしかず)、「和田義盛」(わだよしもり)、「梶原景時」(かじわらかげとき)、「足立遠元」(あだちとおもと)、「三浦義澄」(みうらよしずみ)、「八田知家」(はったともいえ)、「安達盛長」(あだちもりなが)、そして二階堂行政です。
当時、鎌倉幕府と敵対していた朝廷への守りを固めるために、二階堂行政は砦の建築を命じられました。それがのちの岐阜城です。
しかしこの13人の合議制は、発足からわずか1年で梶原景時の失脚や三浦義澄、安達盛長の病死により解体し、源頼家政権も権力闘争の末に崩壊してしまいました。
二階堂行政は1204年(元久元年)に「山城守」(やましろのかみ:京都府南部の守護)を命じられましたが、翌1205年(元久2年)に辞職。その後に二階堂行政が職務を遂行していた記録は見つかっていません。
二階堂行政は、武士として華々しい武功を上げた訳ではありませんが、文官という立場で鎌倉幕府を裏から支えました。また子孫も鎌倉幕府の重職に就任しており、室町幕府まで二階堂の姓を残しています。




![]()