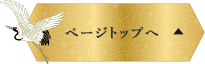日本の城と戦国武将
毛利輝元(毛利輝元と城一覧)

毛利輝元(毛利輝元と城一覧)/ホームメイト
「毛利輝元」(もうりてるもと)は、1553年(天文22年)1月22日から1625年(寛永2年)4月27日まで生きた戦国大名です。



![]()
- 小
- 中
- 大
毛利輝元とゆかりの城について、その歴史を紐解いていきましょう。
「毛利輝元」(もうりてるもと)は、1553年(天文22年)1月22日「吉田郡山城」(よしだこおりやまじょう:現在の広島県安芸高田市)にて、名将として名高い「毛利元就」の孫として生まれ、1625年(寛永2年)4月27日まで生きた戦国大名です。豊臣家五大老のひとりであり、毛利輝元の「輝」は、室町幕府第13代将軍「足利義輝」から一字を賜っています。
また、毛利輝元は山陽・山陰8ヵ国112万石を統治した有力大名でありながら、室町幕府最後の将軍「足利義昭」を匿ったために「織田信長」と対立。また、天下分け目の「関ヶ原の戦い」や「大坂の陣」では、戦いに弱腰とも捉えられるような行動をするなど、大きな影響力を持つ大名であるがゆえの危うさや苦悩を抱えていたとされています。
毛利輝元は1589年(天正17年)当時の交通の要衝である太田川(現在の広島県廿日市市)の三角州に、「広島城」(現在の広島県広島市)の築城を開始しました。広島城は、毛利輝元が上洛時に見聞した「聚楽第」(じゅらくてい:京都市上京区)、「豊臣秀吉」の「大坂城」(大阪市中央区)に感化されて築城。今回は、毛利輝元の生涯と、ゆかりの深い城についてご紹介します。