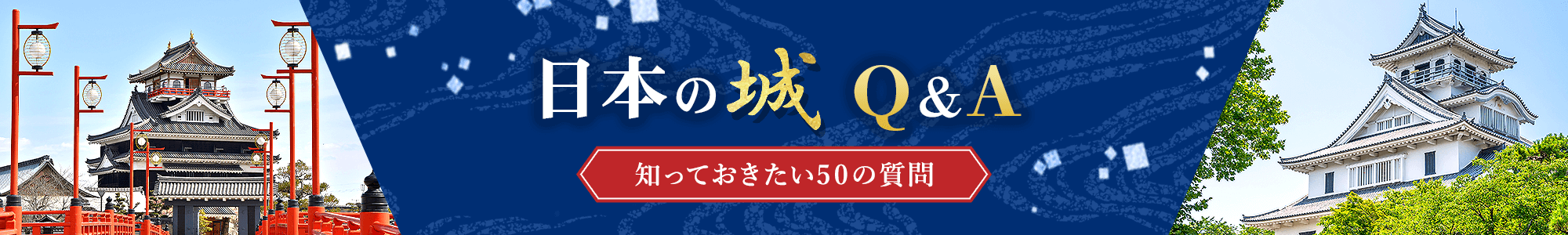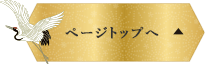どうやって石を運んだの?
運べる程度の大きさにしてから運ばれました。

石垣を築くには、まず石材が必要です。石材は運ぶ前に、まず運べるくらいの大きさに切り出します。大きな石材に穴を点々と直線状に開けたあと、その穴に矢を入れて、上から金づちを使って突いて割っていました。この穴は「矢穴」と呼ばれ、「江戸城」(東京都千代田区)をはじめ、数々の城の石垣で見ることができます。
切り出された石材は、持ち運べる大きさの場合、人が背負子(しょいこ:背負って運搬するための器具)やカゴを使って運びました。あまりに大きな巨石は、木製の大型ソリ「修羅」(しゅら)が用いられていたと言われています。なお、遠方に運ぶ場合は、船やいかだを用い、水路で運搬されていました。
石材の運び方で面白い説は、大阪城の巨石運搬に関するエピソード。なんと、修羅のすべりをよくするために、昆布のぬめりを活かしていたという説があります。