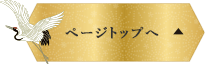城・日本の城・城郭用語辞典


![]()
- 小
- 中
- 大
-
塀
へい塀とは、外部からの侵入防止や目隠しなどの目的で、住宅や各種施設などの敷地の境界に建てられる障壁のこと。中世や近世の城においても、曲輪(くるわ)を区画したり、塁上に設けて防衛力を強化したりするために塀が多用された。当初は板塀で、柵に板を付けた物や盾を複数並べることが行なわれた。しかし、火に弱いと言う板塀の欠点を克服するため、次第に板表面に土や漆喰などを塗るようになり、塗塀が生まれた。さらに土で造った土塀なども考案される。城に用いられた塀としては、柱や板を中心に立ててから泥土で突き固めて屋根を載せる「築地塀」(ついじべい)や、漆喰の塗り壁の下部に平瓦を張る「海鼠塀」(なまこべい)、軒先に鋭利な刃物を付けた「剣塀」(つるぎべい)などがある。
全国から日本の城を検索
全国からご希望の都道府県を選択すると、各地域の日本の城を検索できます。