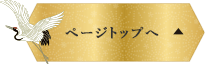城・日本の城・城郭用語辞典


![]()
- 小
- 中
- 大
-
登り石垣
のぼりいしがき登り石垣とは、日本の城における石垣の建造方法のひとつである。山上に天守閣があり、山のふもとに兵士の住む建物などがある城において、山頂の天守閣とふもとの施設を囲むように、山の斜面の両側にも石垣を構築した物。中国の「万里の長城」のように、山腹から敵が侵入するのを防ぐことに役立つ。豊臣秀吉が16世紀後半に朝鮮出兵を行なった際、日本遠征軍が使う安骨浦(アンゴルポ)城の築城において考案された手法と伝わる。この朝鮮出兵に参加していた脇坂安治や加藤嘉明らがその手法を持ち帰って、国内の築城にも生かした。実際には登り石垣が国内で造られた例は非常に少なく、現存する十数ヵ所ある天守の城郭のなかでも、その存在が確認されているのは愛媛県の松山城と滋賀県の彦根城だけである。
全国から日本の城を検索
全国からご希望の都道府県を選択すると、各地域の日本の城を検索できます。