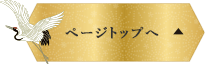城・日本の城・城郭用語辞典


![]()
- 小
- 中
- 大
-
西の丸
にしのまる西の丸とは、日本の各城において最も主要な曲輪(くるわ)とされる本丸の西のほうに、独立して設けられた曲輪を意味する。曲輪とは土塁や石垣などで仕切られた一定の区画のことである。日本の城は曲輪をいくつも配置する形で構成され、本丸の周りには二の丸が置かれてきたが、西の丸は徳川家康が江戸城に初めて造営したのをきっかけに各地の城に造られるようになった。西の丸は、世代交代をした城主が隠居場所として使うのが基本で、城主の妻や世継ぎとなる子が住むこともあった。城主の家族が私的に利用する区画とも言える。例えば、姫路城の西の丸は、徳川秀忠の娘である千姫が本多忠刻と再婚する際にその化粧料十万石をもって造営された物で、大奥のような役割を持っていた。
全国から日本の城を検索
全国からご希望の都道府県を選択すると、各地域の日本の城を検索できます。