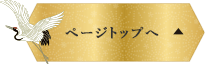城・日本の城・城郭用語辞典


![]()
- 小
- 中
- 大
-
土橋
どばし土橋とは、一般的には木の橋をベースにしながら土をかけて整えた橋のことを意味する。中世や近世の城における土橋はやや意味が異なり、虎口(こぐち)の前にあって堀を横断する物で、通路となるところの地面を掘り残した形状の橋を指す。土居や石垣で築かれることが多く、堀のなかに水を入れる水堀である場合は、土橋を挟んで右側は水量を増やし、逆に左側は水量を減らすなど、水位を調整することもできた。敵が船で移動するのを防ぐ目的もあったと考えられる。通常の架け橋のように撤去することはできないが、いつでも出撃しやすいので攻撃本位の橋との解釈もある。代表的な土橋の例としては、東京都の江戸城牛込門・半蔵門・清水門・田安門、大阪府の大阪城桜門など。
全国から日本の城を検索
全国からご希望の都道府県を選択すると、各地域の日本の城を検索できます。