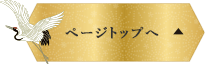城・日本の城・城郭用語辞典


![]()
- 小
- 中
- 大
-
外城制
とじょうせい外城制とは、安土桃山時代から江戸時代にかけ、薩摩藩において独自に実施された制度の名称である。領地のなかを外城と言う区画に分けた物で、それぞれの外城に地頭や武士を配置して軍事や政治などを行なうようにした物。ひとつの外城に数村、多いところでは数十村が含まれる。薩摩藩を支配していた島津氏が独自に行なった物で、幕府の制度とは関係がない。1615年(慶長20年)に江戸幕府より一国一城令が公布されると、島津氏の居城であった鶴丸城の他の城は廃止されたが、外城制その物は残り、各区域を統治する役の者が鶴丸城下に住みながら地頭を務めた。外城と言う用語は、内城である鶴丸城に対する物である。
全国から日本の城を検索
全国からご希望の都道府県を選択すると、各地域の日本の城を検索できます。