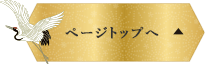城・日本の城・城郭用語辞典


![]()
- 小
- 中
- 大
-
胴木
どうぎ胴木とは、日本の城における石垣の構成要素である木材のこと。石垣とは、城の守備力を高めるために、石を使って高く積み上げた塁のことである。側面の表面には大きな石を配して固め、内側には直径10〜30cm程度の小石を多数詰め込んで構成する。最下部には根石と呼ばれる大石を敷くが、根石が石の重さや地盤の弱さなどによって沈下したり他の石とのバランスが悪くなったりすると、石垣全体が崩壊することもある。こうした根石のバランスを保つために、その下に敷かれるのが胴木である。胴木には土や水による腐食に強い松の丸太が適しているとされ、質の良い物では数百年から千年くらいは使い続けることができる。
全国から日本の城を検索
全国からご希望の都道府県を選択すると、各地域の日本の城を検索できます。