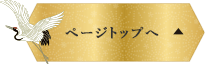城・日本の城・城郭用語辞典


![]()
- 小
- 中
- 大
-
転用石
てんようせき転用石とは、日本の城において、もともとは違う目的に使われていたものの、石垣に組み込まれることになった石のことを意味する。転用石として採用された物は墓石や石臼、石仏や燈籠、五輪塔と言った寺社にある石でできた造形物などが多く、寺院や領民などから収集されている。転用石が必要になる背景には、戦国時代に入って城や石垣が増加して石材が不足したこと、急な築城で予定の日程までに石が調達できなかったときなどに発生したとされる。また、攻め落とした領地に新しい主が来たときには、かつての領主の墓地から石を集めて転用石とすることもあり、これには権力者の威厳を表わす意図もあったと考えられる。転用石がたくさん使われた城としては京都府の福知山城、奈良県の大和郡山城などがある。
全国から日本の城を検索
全国からご希望の都道府県を選択すると、各地域の日本の城を検索できます。