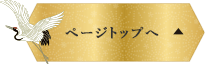城・日本の城・城郭用語辞典


![]()
- 小
- 中
- 大
-
天守閣
てんしゅかく天守閣とは、日本の城郭建築のなかでも中核となる施設である。天守閣は明治時代以降の呼び名であり、それ以前は天守、殿守、天主などと称されていた。城郭のなかでは最も高層の建築物とされるのが一般的。天守閣が果たす機能は、城の主が指揮を執る場所になることの他に、儀式を行なったり、高い位置から遠くを監視したり、物資を収納しておく倉庫になることなどがある。城主の権威の象徴としての役割もあり、城郭のなかでも最も格の高い櫓(やぐら)と言える。天守閣は日本の城に欠かせない物としてイメージされることがあるが、実際には安土桃山時代以降に広まった物であり、天守閣を持たない城も多い。現存する天守閣がある城は青森県の弘前城、長野県の松本城、福井県の丸岡城、愛知県の犬山城など12ヵ所。この他、大阪府の大阪城のように復興または復元された天守閣が建っているケースもある。
全国から日本の城を検索
全国からご希望の都道府県を選択すると、各地域の日本の城を検索できます。