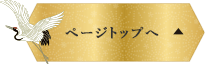城・日本の城・城郭用語辞典


![]()
- 小
- 中
- 大
-
築地塀
ついじべい築地塀とは、粘土や泥土などを厚く塗って固めた塀で、上に屋根が載せられているのが特徴である。中世や近世の城に採用された例がある。親柱を立てて、表面は漆喰で塗り込める方法が一般的。柱や板を組んで建てた物を骨組みとする場合もあれば、横筋が付けられる場合もある。日本では古くから貴族の邸宅や寺院などに用いられてきたが、そのときには土塁のように泥をつき固めた程度の物であった。次第に城の区画内にも築地塀が登場するようになると、塀の上にはカヤやワラ、板などで屋根が造られた。近世になると城郭における屋根の素材には瓦が多いが、これは松永久秀の居城として知られる奈良県(大和)の多聞城で設けた物が最初と伝わる。
全国から日本の城を検索
全国からご希望の都道府県を選択すると、各地域の日本の城を検索できます。