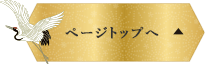城・日本の城・城郭用語辞典


![]()
- 小
- 中
- 大
-
竪堀
たてぼり堅堀とは、日本の城に関する用語のひとつで、堀の一種。堀とは、地面を細長く掘った構造のことを意味し、戦国時代には敵が城に攻め入ったり、動物が侵入したりするのを防ぐ目的でほとんどの城で採用された。通常、城の堀は本丸など中核施設を取り囲むような位置にぐるりとめぐらされるが、堅堀は山城などにおいて山の上から下方向へ、縦に造られるのが特徴である。これにより、敵が斜面をつたって山上の城へ押し寄せたり、山腹で横に移動したりするのを阻むのに役立つ。中世の山城では石垣がなく、防御用の施設として堅堀を造ることが多かった。堅堀には数本を並べた畝状堅堀や、いくつかの堀を横に連接した連続堅堀がある。岐阜県の市場城の跡地など、各地で堅堀を見ることができる。
全国から日本の城を検索
全国からご希望の都道府県を選択すると、各地域の日本の城を検索できます。