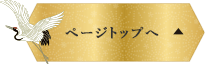城・日本の城・城郭用語辞典


![]()
- 小
- 中
- 大
-
対城
たいのしろ対城とは、日本の戦国時代において、城攻めのときに攻める側の軍が相手に対して陣を敷くために、攻略を目指す城の近くに築く臨時の城のことである。向城、付城などと同じ意味で使われる。城を守る側が籠城作戦を採る場合などに、攻め手が築城することがある。短い期間で築城され、城攻めが済んだあとには取り壊されるのが一般的。対城の代表的な例としては、1590年(天正18年)に豊臣秀吉が北条氏を制圧しようとした小田原攻めの際の石垣山城がある。この城は石垣山一夜城とも呼ばれ、わずかな期間では到底建造できない程の立派な城を秀吉が一晩で造り上げたように見せたことで、小田原城のなかにいた将兵が衝撃を受け、士気を失ったと言う逸話を残している。
全国から日本の城を検索
全国からご希望の都道府県を選択すると、各地域の日本の城を検索できます。