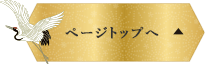城・日本の城・城郭用語辞典


![]()
- 小
- 中
- 大
-
城柵
じょうさく城柵とは、大和朝廷が日本に君臨していたころに築いた軍事的拠点、あるいは行政を執行するための施設である。古代において東北に住んでいた民族である蝦夷(えぞ)を平定して国家を拡大する目的で、主に東北地方に建造された。厳密には城(き)と柵(き)と言う2種類に分類され、日本書記や続・日本書紀に「城柵」とまとめた形で登場している。柵は本拠の周りに空堀をめぐらし、20〜30cmの高さの木材を地面に縦に差し込んで柵のように並べた物。丘の上におかれ、中心部には寺社があり、住民の集落があるなどの形状がとられた。こうした城や柵は多数造られ、それぞれに多賀城、玉造柵などと名称があったとされる。奈良時代以降も城柵は存在し、東北地方などの統治のために用いられていた。
全国から日本の城を検索
全国からご希望の都道府県を選択すると、各地域の日本の城を検索できます。