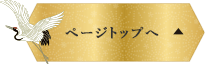城・日本の城・城郭用語辞典


![]()
- 小
- 中
- 大
-
神籠石
こうごいし神籠石とは、日本において城が多く建築された戦国時代よりもはるか昔の、上世のころに造られた列石の遺跡のこと。神籠石式山城とも言う。日本最古の正式な歴史書である「日本書紀」や「続日本紀」に記載がなく、遺構でのみ存在が確認される物を神籠石とするのが一般的。石を整然と並べ、谷や山腹を取り囲むように造られた石垣のような構造物である。その目的は神を祀るためであるとする説と、城の防御設備の一部であるとする説があり、1898年(明治31年)に小林庄次郎氏が「霊地として神聖に保たれた地を区別したもの」として筑後・高良山神籠石を学会で紹介したのを皮切りに論争が巻き起こった。九州地方から瀬戸内地方に多く、詳細は不明であるが国の史跡に指定されている箇所もある。
全国から日本の城を検索
全国からご希望の都道府県を選択すると、各地域の日本の城を検索できます。