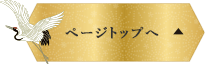城情報
城と刀剣/ホームメイト
江戸時代までに建てられ、現在も天守が残っている城は12あります。このうち、「姫路城」(兵庫県姫路市)、「松本城」(長野県松本市)、「犬山城」(愛知県犬山市)、「彦根城」(滋賀県彦根市)、「松江城」(島根県松江市)の5城が国宝に指定。もともとは軍事目的で建設された城は、名だたる武将達が城主として名を連ねました。そして、城主である武将と刀剣は切っても切れない縁(えにし)で結ばれていたのです。「城と刀剣」では、国宝5城にゆかりの深い刀剣をご紹介していきます。
姫路城と大包平
世界遺産にも登録されている白亜の名城

白漆喰の外壁と、破風(はふ:屋根の妻側の造形)の構成の美しさから、「白鷺城」(しらさぎじょう)とも呼ばれる「姫路城」。1951年(昭和26年)6月9日に国宝に指定され、1993年(平成5年)12月には、奈良県の「法隆寺」とともに日本で初めてユネスコの世界文化遺産に登録されました。

姫路城は、1331年(元徳3年)に播磨国(兵庫県西南部)の守護であった「赤松則村」(あかまつのりむら)が砦(とりで)を築いたのがはじまりとされます。その後、赤松氏に仕えた小寺氏や、黒田氏が姫路城を預かり、1580年(天正8年)には「豊臣秀吉」が3層の天守を築いて拠点とし、中国地方の毛利氏と戦いました。
1600年(慶長5年)、「関ヶ原の戦い」で戦功を挙げた「池田輝政」(いけだてるまさ)が入封。9年の歳月をかけて現在の5層6階地下1階の天守を完成させ、1616年(元和2年)まで池田家3代が城主を務めたのです。
一国にも匹敵する名刀「大包平」
池田輝政は、現在は御物(ぎょぶつ)となっている「若狭正宗」(わかさまさむね)や、「蜂屋江」(はちやごう:明暦の大火で焼失)など数々の名刀を所持したことで知られています。

なかでも「大包平」(おおかねひら)は「一国に替え難い名刀である」と非常に高く評価していました。
大包平は、平安時代末期の刀工「包平」の最高傑作との呼び声が高く、「天下五剣」(てんがごけん)のひとつである「童子切安綱」(どうじぎりやすつな)とともに「東西の両横綱」と並び称されているほどです。長く池田家に伝来していた大包平ですが、1967年(昭和42年)に文部省(現在の文部科学省)が6,500万円で買い上げ、現在は「東京国立博物館」(東京都台東区)に収蔵されています。
松本城と刀 銘 葛尾山麓住人宮入昭平作
石川数正が天守建造をはじめる

松本城は、信濃国(現在の長野県)守護であった小笠原氏が本城とした「林城」(現在の長野県松本市)の支城「深志城」(ふかしじょう)が基礎となっています。

松本城へと改名したのは、1582年(天正10年)の「本能寺の変」後に「徳川家康」に仕えた「小笠原貞慶」(おがさわらざだよし/さだのり)。その後の1590年(天正18年)、「小田原征伐」のあとに信濃国松本を豊臣秀吉より与えられた「石川数正」(いしかわかずまさ)が松本城天守の建造に着手しました。
石川数正は、徳川家康の幼少期より仕えた懐刀(ふところがたな)とも言える重臣でしたが、豊臣秀吉のもとへ出奔したことで有名です。
松本城の天守を完成させたのは石川数正の長男「石川康長」(いしかわやすなが)ですが、江戸時代初期に改易(かいえき)となりました。以降、ふたたび小笠原氏が城主を務めたのをはじめ、明治維新までに6家23人が城主となっています。
長野県出身の現代刀匠が手がけた「刀 銘 葛尾山麓住人宮入昭平作」
松本城のある長野県出身の刀工と言えば、重要無形文化財保持者(人間国宝)の「宮入昭平」(みやいりあきひら:後期の銘は宮入行平[みやいりゆきひら])刀匠がよく知られているのではないでしょうか。

宮入昭平刀匠の息子である「宮入小左衛門行平」(みやいりこざえもんゆきひら)刀匠や甥の「宮入法廣」(みやいりのりひろ)刀匠、弟子の「高橋次平」(たかはしつぐひら)刀匠、「古川清行」(ふるかわきよゆき)刀匠も長野県出身です。
「刀剣ワールド財団」が所蔵する「刀 銘 葛尾山麓住人宮入昭平作」(かたな めい かつらおさんろくじゅうにんみやいりあきひらさく)は、「第2次世界大戦」後期にあたる1944年(昭和19年)の作品。時節柄、軍刀として鍛えられた刀ですが、体配は豪壮にして、小板目が詰んだ地鉄(じがね)は明るく肌立ち、刃文は丁子(ちょうじ)交じりの互の目乱れ(ぐのめみだれ)に小沸(こにえ)が付いて冴えています。
戦地へおもむく将校の武運長久を祈念して丁寧に作刀した、宮入昭平刀匠の想いすら垣間見える1振です。
犬山城と左安吉作/正平十二年二月日
小牧・長久手の戦いでは豊臣秀吉の本陣となる

犬山城は、もともとあった岩倉織田氏の砦を、1532~1555年(天文年間)に「織田信長」の叔父「織田信康」(おだのぶやす)が改修して築いたと言われています。
1565年(永禄8年)、織田信長が尾張国(現在の愛知県西部)を統一したのち、織田家重臣の「池田恒興」(いけだつねおき)や織田信長の五男(または四男)である「織田勝長」(おだかつなが)が城主を務めました。
1584年(天正12年)の「小牧・長久手の戦い」では、豊臣秀吉が本陣を敷いて「小牧山城」(愛知県小牧市)の徳川家康とにらみ合っています。
江戸時代の1617年(元和3年)には尾張藩付家老の「成瀬正成」(なるせまさなり)が入城。江戸時代を通じて成瀬家9代が城主を務めました。
2004年(平成16年)まで犬山城は成瀬家の個人所有でしたが、保全・管理に困難が伴うことから「公益財団法人 犬山城白帝文庫」(こうえきざいだんほうじん いぬやまじょうはくていぶんこ)が設立され、現在は法人所有となっています。
犬山市文化史料館が保管する「短刀 銘 左安吉作」
犬山城主の成瀬家に伝えられた逸品の短刀が「短刀 銘 左安吉作/正平十二年二月日」(たんとう めい さやすよしさく/しょうへいじゅうにねんにがつひ)です。
作者は南北朝時代に活躍した「左文字派」(さもんじは)の刀工「2代 安吉」(やすよし)。本短刀の差表(さしおもて:腰に差したとき外側になる面)には、「三鈷柄」(さんこづか:密教法具のひとつ)の毛彫と「素剣」(三鈷柄剣を簡略化した彫刻)の浮彫が連続し、連樋(つれひ)が添えられています。
本短刀は1940年(昭和15年)に重要文化財に指定。現在は犬山城白帝文庫が所蔵し、「犬山市文化史料館」(愛知県犬山市)にて保管・展示されています。

- 銘
-
左安吉作
正平十二年二月日
- 時代
-
南北朝時代
- 鑑定区分
-
重要文化財
- 所蔵・伝来
-
成瀬家→
公益財団法人
犬山城白帝文庫
彦根城と(金粉銘)弘行 琳雅(花押)
井伊直政が築城を計画

琵琶湖のほとりに彦根城を築城したのは、徳川家の家臣で近江彦根藩(現在の滋賀県彦根市)2代藩主「井伊直勝」(いいなおかつ)です。

最初に築城を計画したのは、井伊直勝の父である彦根藩初代藩主「井伊直政」(いいなおまさ)でした。井伊直政は「徳川四天王」のひとりに数えられ、また旧武田家の「赤備え」を受け継ぎ、勇敢な家臣団を率いて「井伊の赤鬼」と呼ばれた勇将です。
ところが、井伊直政は関ヶ原の戦いで負ったケガが癒えず、1602年(慶長7年)に死去。井伊直政の遺臣である家老の「木俣守勝」(きまたもりかつ)が徳川家康に相談して、琵琶湖を望む彦根山に彦根城の築城をはじめます。
彦根城は天下普請(てんかぶしん:江戸幕府が全国の大名に命じて行わせる土木工事)により1622年(元和8年)に完成しました。
井伊家伝来の刀「(金粉銘)弘行 琳雅(花押)」
この彦根城主35万石の井伊家に伝えられた刀が「刀剣ワールド財団」所蔵の「(金粉銘)弘行 琳雅(花押)」([きんぷんめい]ひろゆき りんが[かおう])です。
作者の「弘行」は、南北朝時代に筑前国(現在の福岡県西北部)で活躍した左文字派の刀工。左文字派は「相州伝」の伝法に通じていたとされ、多くの名刀を残しています。
本刀は、大磨上げ(おおすりあげ)が施されているものの、反りの浅い体配は身幅が広く大鋒/大切先(おおきっさき)で南北朝時代の時代色が明らかです。
刃文は中直刃を基調に浅く湾れ(のたれ)、匂(におい)深く、沸(にえ)厚く強く付き、太い金筋・砂流し(すながし)が目立ちます。地鉄は板目肌に大板目・杢目(もくめ)交じり。地沸(じにえ)厚く、総じて黒味を帯びているのが特徴的です。刃中の働きも豊かで、出色の出来映えと言えます。
松江城と小太刀 銘 長光
最も新しく国宝指定された名城

島根県松江市にある松江城の天守は、国宝5城の中で唯一平成時代の2015年(平成27年)に国宝指定されました。
松江城を近世城郭として完成させたのは、豊臣秀吉に仕えて中老を務めた「堀尾吉晴」(ほりおよしはる)です。
松江城の城主は、堀尾吉晴の子「堀尾忠氏」(ほりおただうじ)からその子の「堀尾忠晴」(ほりおただはる)へ受け継がれますが、堀尾忠晴に跡継ぎがなかったために堀尾氏は改易。若狭国小浜藩(現在の福井県敦賀市)より「京極忠高」(きょうごくただたか)が入封(にゅうほう)します。
ところが、京極忠高も跡継ぎなく没したため、信濃国松本藩(現在の長野県松本市)より徳川家康の孫にあたる「松平直政」(まつだいらなおまさ)が入封。明治維新まで松平家が松江城主を務めました。
結城秀康から伝えられた「小太刀 銘 長光」
明治維新まで、10代にわたり城主を務めた松平家に伝えられた刀剣が「小太刀 銘 長光」(こだち めい ながみつ)です。
本太刀は、徳川家康の次男「結城秀康」(ゆうきひでやす)が所持し、のちに三男の松平直政へ渡りました。
作者の「長光」は、備前国長船(現在の岡山県瀬戸内市)の刀工で鎌倉時代中期に活躍。「長船派」の流祖とされる「光忠」(みつただ)の子と伝えられています。
本刀は太刀よりも刃長の短い小太刀に分類され、太刀のように刃を下にして佩用しました。
現在、島根県松江市にある「松江歴史館」が収蔵。島根県指定有形文化財(工芸品)となっています。
- 銘
-
長光
- 時代
-
鎌倉時代中期
- 鑑定区分
-
島根県指定
有形文化財
- 所蔵・伝来
-
結城秀康→
松平家→
松江歴史館収蔵