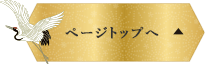城情報
関東七名城とは/ホームメイト
関東地方には、戦国時代に要衝として活用された「関東七名城」(かんとうしちめいじょう)と称される7つの城があります。「夏目定房」(なつめさだふさ)という人物が、かつて父が仕えた「上杉氏」(うえすぎし)や「夏目氏」(なつめし)について記した軍記物「管窺武鑑」(かんきぶかん)のなかで7つの城を選出。そのため、「上杉謙信」(うえすぎけんしん)の関東遠征にまつわる城郭が中心となっているのが特徴です。戦国時代に激しい攻防戦の舞台となった難攻不落の7つの名城を、順番に紹介していきます。
宇都宮城

「宇都宮城」(うつのみやじょう:栃木県宇都宮市)は、関東地方屈指の歴史を持つ城郭です。平安時代に築城されたと考えられていますが、正確な築城年は定かではありません。
北関東の雄として下野国(しもつけのくに:現在の栃木県)で勢力を誇った「宇都宮氏」(うつのみやし)の居城であり、江戸時代に入ると大改修が行われ、「徳川氏」(とくがわし)の重臣達が代わる代わる入封(にゅうほう:新しい領地を与えられ、その土地に入ること)。特に1619年(元和5年)から3年間この地を治めた「本多正純」(ほんだまさずみ)による城と城下町の整備は、現在の宇都宮市の礎となりました。
しかし、「明治維新」に伴う混乱のなかでほとんどの建造物が焼失。その後の開発や戦後復興によって、遺構も大部分が失われてしまいました。
当初は、本丸にあたるエリアに土塁の一部が残るのみとなっていた宇都宮城ですが、復元作業を経て2007年(平成19年)に「宇都宮城址公園」(うつのみやじょうしこうえん)として開園。復元されたのは本丸のうち西側の一部で、コの字型の土塁や水堀、櫓(やぐら)などが見られます。
宇都宮城の防御の要であった土塁は、江戸時代の規模を忠実に再現しており、高さは約10m。土塁の上には「白漆喰総塗籠」(しろしっくいそうぬりこめ:白い漆喰ですべて塗り固めること)の土壁が走り、天守の役目を果たしていた「清明台櫓」(せいめいだいやぐら)や「富士見櫓」(ふじみやぐら)が見られます。なお、2つの櫓の内部は見学することもできますが、2階に上がることはできません。忠実に復元したことによって、現在の建築基準法を満たしていないためです。
また、幅約20mの水堀のそばにある土塁は現在コンクリートで補修され、その内部には宇都宮の歴史などを学べる展示室を設置。本丸内部には、同じく歴史展示室などを備える「清明館」(せいめいかん)もあり、いずれも無料で見学が可能です。
宇都宮城址公園は防災公園もかねていることから、本丸内部は大半が芝生広場。しかし、本丸御殿や本来の出入り口だった「清水門」、「伊賀門」の復元も計画されています。
ちなみに、最盛期の宇都宮城は約1㎞四方にわたる規模だったため、宇都宮城址公園以外でも遺構を見ることが可能です。500mほど離れた繁華街そばの「旭町の大いちょう」(あさひちょうのおおいちょう)は、本多正純によって植えられたと伝わる古木。高さ約33mにも及び、現存する土塁の上にそびえ立つ姿は市民のシンボルとしても愛され、宇都宮市の天然記念物にも指定されています。
宇都宮城の施設情報
| 施設名 | 宇都宮城址公園 |
|---|---|
| 所在地 | 〒320-0817 栃木県宇都宮市本丸町1-15 |
| 電話番号 | 028-632-2222 |
| 営業時間 | 櫓などの歴史建築物と展示施設:9:00~19:00 |
| 休業日 | 年末年始 |
| 料金 | 無料 |
| 交通アクセス | 東武宇都宮線「東武宇都宮駅」下車 徒歩:約9分 |
太田城

「太田城」(おおたじょう:茨城県常陸太田市)は、約470年にわたって常陸国(ひたちのくに:現在の茨城県)を治めた「佐竹氏」(さたけし)の拠点だった城郭です。
その起源は定かではありませんが、一説によると平安時代の築城。2代当主「佐竹隆義」(さたけたかよし)のころ、初めて佐竹氏が入城した際に上空を鶴が舞ったという伝説から「舞鶴城」(まいづるじょう)の異名を持つ他、佐竹氏にちなんで「佐竹城」(さたけじょう)とも呼ばれていました。
城は、常陸太田市街地に突き出すように伸びる馬の背状の「鯨ヶ丘台地」(くじらがおかだいち)にあり、台地の中央部、現在の「常陸太田市立太田小学校」周辺に主郭(しゅかく:城の中心となる区画、本丸)があったと考えられています。
また、最初期は台地の先端部である常陸太田簡易裁判所周辺が城域だったとする説もありますが、戦国時代までの太田城は記録に乏しく、詳細は不明。当時の台地周辺は沼地や谷に囲まれた天然の要害となっており、最大で南北約1㎞にわたる城域を持っていました。ただし、太田城の遺構は宅地開発によってそのほとんどが失われており、目立つ痕跡はありません。
数少ない遺構として、常陸太田市立太田小学校内に土塁の跡が残っており、その傍らに「舞鶴城趾」と銘打たれた石碑が存在。さらに、二の丸跡地に鎮座する「若宮八幡宮」(わかみやはちまんぐう)にも、太田城があったことを示す石碑がひっそりと立てられています。
太田城の施設情報
| 施設名 | 太田城跡(常陸太田市立太田小学校) |
|---|---|
| 所在地 | 〒313-0061 茨城県常陸太田市中城町151 |
| 電話番号 | 0294-72-3111 |
| 営業時間 | 見学自由(敷地外から見学する場合) |
| 休業日 | 無休 |
| 料金 | 無料 |
| 交通アクセス | JR水郡線「常陸太田駅」下車 車:約6分 |
忍城

「忍城」(おしじょう:埼玉県行田市[ぎょうだし])は、15世紀後半に武蔵国(むさしのくに:現在の埼玉県・東京23区・神奈川県の一部)の有力国人(こくじん:地方で実質的にその土地を支配する人)「成田氏」(なりたし)の居城として繁栄した城郭です。
1590年(天正18年)、「豊臣秀吉」による「小田原征伐」(おだわらせいばつ)にあたり、「石田三成」(いしだみつなり)が水攻め(城を水没させたり、川からの水路を断って孤立させたりする作戦のこと)をしたものの、結局落とせなかったという堅城で、平成時代には「和田竜」(わだりょう)さんの小説及び、それを原作とする映画「のぼうの城」(のぼうのしろ)の舞台となって、知名度を上げました。
江戸時代には「阿部氏」(あべし)や「奥平松平氏」(おくだいらまつだいらし)など、1600年(慶長5年)の「関ヶ原の戦い」以前から徳川家の家臣で、大名に取り立てられた「譜代大名」(ふだいだいみょう)が入城し、「江戸城」(東京都千代田区:現在の皇居)を守る重要拠点のひとつとして機能しています。
忍城の周辺はもともと低湿地が広がっており、随所に小島が点在する地形でした。その立地を活かしてあえて埋め立てをせず、それぞれの島を曲輪(くるわ)とすることで、堅固な造りを実現したのが忍城です。
城域の中心部は行田市街にあり、本丸跡には「行田市郷土博物館」が建っています。館内では現存遺構のひとつである鐘楼(しょうろう)のうち、1764年(宝暦14年)に鋳造された鐘の本物(屋外の鐘楼ではレプリカを展示)などが観られ、かつての忍城の姿を知ることが可能。
敷地内にも遺構が点在し、忍城のシンボルである「御三階櫓」(おさんがいやぐら)をはじめ、鉄砲狭間(てっぽうはざま:鉄砲を撃つために開けられた小さな窓のような穴)や石垣などが現存しています。
その他、近隣には外堀の名残である沼を活かして整備された「水城公園」(すいじょうこうえん)もあり、歴史散策に適したスポットとして人気です。
忍城の施設情報
| 施設名 | 忍城跡 |
|---|---|
| 所在地 | 〒361-0052 埼玉県行田市本丸17-23 |
| 電話番号 | 048-556-1111 |
| 営業時間 | 9:00~16:30 ※入館16:00まで |
| 休業日 | 月曜日 ※毎月第4金曜日休館 |
| 料金 | 【観覧料】 一般:200円 大高:100円 小中学生:50円 |
| 交通アクセス | 秩父鉄道「行田市駅」下車 徒歩:約10分 |
金山城

「金山城」(かなやまじょう:群馬県太田市)は、「日本100名城」に選出されていることでも名高い山城です。
太田市の中心市街地近くにある独立峰「金山」の地形を活かして築城されており、縄張(なわばり:城の設計)は金山全域に及んでいます。築城は1469年(文明元年)で、もともとは源氏の名門「岩松氏」(いわまつし)の居城として利用されていました。
やがて、重臣「由良氏」(ゆらし)が、下克上により金山城を乗っ取ります。さらに、由良氏も「北条氏」(ほうじょうし)に城を追われたため、以降は1590年(天正18年)に廃城になるまで、北条氏の家臣が城を守りました。
金山城は山城(やまじろ:険しい山の山頂や山腹に建てられた城)でありながらも、石垣や、石敷きの通路を多用しているのが特徴で、関東地方では比較的珍しい、石造りの城となっています。
大規模な土塁や堀切(土塁の尾根を断ち切る堀)などの遺構が残る他、山中に復元された石垣や石畳は見事。「虎口」(こぐち:曲輪の出入り口)や土橋など、堅城ぶりがうかがえる構造物もあり、山頂には大池「日ノ池」(ひのいけ)など、儀式の場所であったと考えられる遺構も見られます。
なお、大規模な山城のため、探索の所要時間は約1時間30分。起伏が激しい城郭のため、訪れる際は動きやすい服装が無難です。
城跡を訪ねる前に、金山の中腹にある「太田市立史跡金山城跡ガイダンス施設」に立ち寄ると、金山城の再現模型や歴史解説などを事前に学ぶことができます。
金山城の施設情報
| 施設名 | 金山城跡 |
|---|---|
| 所在地 | 〒373-0027 群馬県太田市金山町40-98 |
| 電話番号 | 0276-25-1067 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 休業日 | 無休 |
| 料金 | 無料 |
| 交通アクセス | 東武伊勢崎線「太田駅」下車 車:約11分 |
唐沢山城

上杉謙信の攻撃を複数回にわたり撃退した堅城として名高い「唐沢山城」(からさわやまじょう:栃木県佐野市)は、関東随一とも称された山城です。築城時期は定かではありませんが、室町時代と推定されています。
標高約247mの「唐沢山」に築かれており、山頂周辺を本丸として、そこに連なる尾根筋にも複数の遺構が残存。城域は約194ヘクタールにも及びます。
一帯には、周辺を領有していた「佐野氏」(さのし)だけでなく、戦国時代に一時領有していた上杉氏(うえすぎし)や北条氏、さらには「豊臣氏」(とよとみし)が築いた構造物も混在。そのため、多彩な築城文化が見られる城郭としても人気です。
最大の見どころは、8mを越える高石垣。下野国を出奔(しゅっぽん:逃げ出すこと)して豊臣秀吉に仕えた「佐野房綱」(さのふさつな)や、その養子であり豊臣氏家臣「富田氏」(とみたし)の出の「佐野信吉」(さののぶよし)らによって、西国の築城技術を駆使して築かれました。
関東地方では珍しい、「織豊政権」(しょくほうせいけん:「織田信長」と豊臣秀吉が担った政権)の影響を受けた城郭でもあるのです。
山麓にも曲輪の遺構が多く、「蛇堀」(じゃぼり)と呼ばれた水堀の跡や、土塁に切れ目を入れた虎口などが現存。ふもとを流れる秋山川と山裾の間にあり、土塁や堀によって整然と区画されていたことがうかがえます。
また、道路工事によって失われてしまったものの、かつては山の中腹から下方向へ縦に伸びる長大な堀である「竪堀」(たてぼり)も存在しました。
こうした外郭部の遺構は、戦乱が続いていた比較的古い時代の物と推定されており、山頂付近にある戦国時代の遺構とともに、築城技術の変遷を見ることもできます。
唐沢山城の施設情報
| 施設名 | 唐沢山城 |
|---|---|
| 所在地 | 〒327-0801 栃木県佐野市富士町 |
| 電話番号 | 0283-24-5111 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 休業日 | 無休 |
| 料金 | 無料 |
| 交通アクセス | 東武佐野線「田沼駅」下車 徒歩:約45分 |
川越城

「川越城」(かわごえじょう:埼玉県川越市)は、江戸城を築いたことでも知られる戦国時代の名将「太田道灌」(おおたどうかん)と、その父「太田資清」(おおたすけきよ)によって築かれました。
川越城は、太田親子の主君でもある「扇谷上杉氏」(おうぎがやつうえすぎし)の居城として整備され、1454年(享徳3年)に起こった「享徳の乱」(きょうとくのらん:足利氏と上杉氏の戦い)や、1487年(長享元年)に起こった「長享の乱」(ちょうきょうのらん:山内上杉家と扇谷上杉氏との戦い)といった、関東地方全土にまたがる大乱に巻き込まれ、やがて扇谷上杉氏と北条氏の争いにおける拠点となっていきます。
日本三大夜戦に数えられる1546年(天文15年)の「河越夜戦」(かわごえやせん:北条氏と上杉氏・足利氏の連合軍との戦い)はその代表例で、川越城は関東地方南部に覇を唱えた扇谷上杉氏の実質的な終焉地にもなりました。
江戸時代に入ると、川越城の城下町は武蔵国有数の都市として栄え、現在は「小江戸」と称される観光地として人気の街に発展。一方で、開発により城の遺構はほとんどが失われてしまっています。
台地の先端部に位置していた川越城は、複数の河川や湿地帯に囲まれた天然の要害でした。そんな地形のなかに複数の独立した曲輪を築き、堀で囲んだ上で土橋や虎口などの防御施設を構築。難攻不落の城として名高く、河越夜戦では「北条綱成」(ほうじょうつなしげ)が、約3,000人の兵力で、およそ8万人もの大軍の攻撃をしのぎ切っています。
しかし、最大でおよそ5万坪に及ぶ敷地を有していたとされているものの、現存する遺構は1848年(嘉永元年)に建てられた「本丸御殿」のみ。とは言え、本丸御殿が現存するのは全国でも川越城を含む数ヵ所のみとなっており、江戸時代の大名による建築様式を伝える貴重な遺構として、注目されています。
ただし、地形から当時の城郭を想起できるスポットは複数あり、本丸御殿の南西に鎮座する「浅間神社」(せんげんじんじゃ)と「御嶽神社」(みたけじんじゃ)は、川越城の「富士見櫓」(ふじみやぐら)の跡地。城内でもっとも高い場所にあたり、天守の役目を果たしていたと推定されています。
川越城の施設情報
| 施設名 | 川越城 |
|---|---|
| 所在地 | 〒350-0053 埼玉県川越市郭町2-13-1 |
| 電話番号 | 049-222-5399 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 休業日 | 月曜日、年末年始、館内整理日(休日を除いた毎月第4金曜日) ※月曜日が休日の場合は翌日 |
| 料金 | 【観覧料】 一般:100円 大高:50円 中学生以下:無料 |
| 交通アクセス | 西武新宿線「本川越駅」下車 徒歩:約18分 |
前橋城

古くは「厩橋城」(まやばしじょう)とも呼ばれ、上杉氏と北条氏の争いの場となったのが「前橋城」(まえばしじょう:群馬県前橋市)です。
15世紀後半に「長野氏」(ながのし)によって築城されたのちに上杉謙信の支配下となり、上杉謙信による関東遠征の拠点として用いられました。
一方で、たびたび北条氏によって奪取されており、上杉氏の撤退後、豊臣秀吉による小田原征伐までの期間の多くは北条氏の属城。
江戸時代に入ると、付近を流れる利根川の侵食や水害に悩まされたこともあり、一度廃城になりますが、幕末期には江戸城に代わる拠点のひとつとして再び築城されました。
明治維新後は本丸跡地に群馬県庁が建てられ、現在に至るまで群馬県庁が置かれています。
群馬県の主要機関が集中している上に市街地の中心部であることから、前橋城の遺構はほとんど残っていません。
見られるのは、三の丸への城門であった「車橋門」(くるまばしもん)の跡地である石垣や、群馬県庁の周辺に残る土塁など。県庁の北側にある「楽歩堂前橋公園」(らくほどうまえばしこうえん)には、土塁のほかに砲台跡が見学できます。
また、前橋市郊外にある「大興寺」(だいこうじ)には、城門や最後の城主「松平直方」(まつだいらなおかた)の邸宅を移築。前橋城の面影を留める、貴重なスポットとして人気です。
前橋城の施設情報
| 施設名 | 前橋城跡 |
|---|---|
| 所在地 | 〒371-0026 群馬県前橋市大手町1-1-1 |
| 電話番号 | 027-224-1111 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 休業日 | 無休 |
| 料金 | 無料 |
| 交通アクセス | 上毛電気鉄道上毛線「中央前橋駅」下車 徒歩:約15分 |