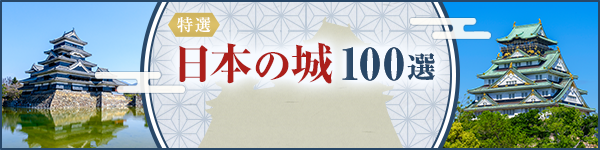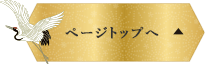城情報
日本三大山城とは/ホームメイト
全国に約2万存在すると言われる「山城」(やまじろ:険しい山の山頂や山腹に建てられた城)のうち、特に防御施設の充実ぶりや規模において優れている3つの城郭を「日本三大山城」(にほんさんだいやまじろ)と言います。名を連ねているのは「岩村城」(いわむらじょう:岐阜県恵那市)、「高取城」(たかとりじょう:奈良県高市郡高取町)、「備中松山城」(びっちゅうまつやまじょう:岡山県高梁市)の3城。それぞれの歴史や特徴を、現存する遺構とともに紹介します。
日本三大山城とは
そもそも山城とは、外敵からの侵攻に備えて、山などの高所に築かれた防御施設を指します。弥生時代に形成された「高地性集落」(こうちせいしゅうらく)が起源と言われ、やがて軍事的機能を強化した城郭へと発展しました。
とりわけ戦国時代に入ると山城の必要性が高まり、爆発的に増加。さらに時代を追うごとに規模の拡大や防御設備の複雑さが増し、難攻不落の堅城が次々と誕生したのです。
その代表格が、岩村城や高取城、備中松山城によって構成された日本三大山城。いずれも最初に築かれたのは鎌倉時代ごろですが、築城技術の発達に伴って改修や整備が繰り返され、戦国時代には壮大な山城へと進化しました。
特に日本三大山城が人気を集めている大きな理由が、遺構の豊富さです。壮大な石垣や緻密な「虎口」(こぐち:城や、城を囲う曲輪[くるわ]の出入り口)などの保存状態が良く、訪れるとタイムスリップ感覚で散策することが可能。近世城郭の粋をじかに見ることができます。
つまり日本三大山城とは、築城時の堅固さだけでなく、現地での史跡探索の楽しみもかね備えた歴史スポットなのです。
岩村城

岩村城(別名「美濃岩村城」)は、近世城郭のなかで、最も高所に本丸が置かれていることで知られる山城です。
その高さは約717mに及び、山肌を覆うように石垣が広がっています。
築城は1185年(文治元年)までさかのぼり、戦国時代には「武田氏」(たけだし)と「織田氏」(おだし)の間で熾烈(しれつ)な争奪戦が繰り広げられました。
岩村城を巡る逸話のなかで特に有名なのが、織田氏の傘下に入っていた時期、城主「遠山景任」(とおやまかげとう)の妻「おつやの方」が、夫の死後に女城主を務めていたことです。
1572年(元亀3年)に甲斐国(かいのくに:現在の山梨県)の「武田信玄」(たけだしんげん)が京を目指して「西上作戦」(せいじょうさくせん)を開始すると、岩村城にも武田軍が襲来。ここでおつやの方は果敢に指揮を執り、敵を大いに驚かせたと言います。
やがて降伏勧告を受け入れて、城主は武田氏の猛将「秋山虎繁」(あきやまとらしげ)が担いますが、おつやの方は秋山虎繁と再婚。1582年(天正10年)に織田氏が「甲州征伐」(こうしゅうせいばつ)を行い、落城の末に夫婦ともども磔刑(たっけい:はりつけの刑)に処されるまで、城を守りました。
現在、城跡は県指定史跡として整備され、往時の姿を留めています。そのなかでも特にシンボルとなっているのが、本丸に築かれた6段の石垣です。戦国時代は1段の高石垣のみがそびえていましたが、江戸時代に崩落防止のため積み直され、ひな壇状の姿になりました。整然と連なる姿が美しく、岩村城最大の撮影スポットとしても人気です。
その他、山麓には藩主邸宅跡があり、「太鼓櫓」(たいこやぐら)や「表御門」(おもてごもん)などが模擬建設されています。
また、藩主邸宅跡から延びる大手道(おおてみち)を登っていくと、「堀切」(ほりきり:尾根を分断した堀)や曲輪、「霧ケ井」(きりがい)と呼ばれる井戸の跡などが点在。かつての「縄張」(なわばり:城郭の設計)の壮大さが実感できます。
ふもとから山頂まで徒歩約30分。道が整備されており、比較的歩きやすいのも魅力です。
| 施設名 | 岩村城跡 |
|---|---|
| 所在地 | 〒509-7403 岐阜県恵那市岩村町城山 |
| 電話番号 | 0573-43-3231(恵那市観光協会岩村支部) |
| 営業時間 | 散策自由 |
| 休業日 | 無休 |
| 料金 | 無料 |
| 交通アクセス | 明知鉄道「岩村駅」下車 車:約10分 |

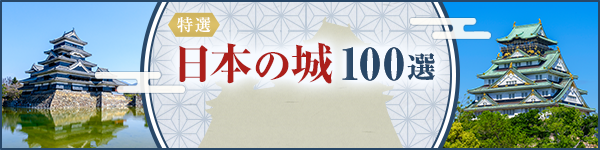
高取城

日本一の比高(ひこう:高低差のこと)を誇る山城が、高取城(別名「大和高取城」)です。
標高約584mの高取山山頂に築かれ、ふもととの比高は約390m。中心部の城内は周囲約3kmながら、曲輪を含んだ「郭内」(かくない)は約30kmに及ぶ広大さを誇りました。言わば、二重の防御網が展開された、戦国時代最大級の山城なのです。
起源は1332年(元弘2年)、南北朝の争乱(朝廷が奈良・吉野の南朝と京都の北朝のふたつに分かれて対立していたこと)で南朝に属していた「越智氏」(おちし)が築城したこと。
当時は天守や櫓のない簡素な造りでしたが、時代を追うごとに拡張され、次第に大規模な山城へと変貌を遂げていきました。
その後、1580年(天正8年)には「織田信長」の命令で一度廃城となりますが、1584年(天正12年)に大和国(やまとのくに:現在の奈良県)の大名「筒井順慶」(つついじゅんけい)が再建。以降は、豊臣氏に属する大和国の要衝として重要度を高めていきました。
現在の遺構に連なる近世城郭へと姿を変えたのは、「豊臣秀吉」の弟「豊臣秀長」(とよとみひでなが)の所領になってからです。家臣の「本多利久」(ほんだとしひさ)が大改修を行い、山城にもかかわらず平城式(ひらじろしき/ひらじょうしき)の築城法を導入。他に類を見ない壮大な山城へと生まれ変わったのです。
城内には天守をはじめ計27の櫓が設けられ、門の数も33ヵ所。白漆喰塗りによって仕上げられた建造物が山頂を染める姿は美しく、「巽高取(たつみたかとり)雪かとみれば 雪でござらぬ土佐(高取の旧名)の城」と謳われたほどでした。
現在も随所に遺構が残っており、高さ約12mにも及ぶ高石垣や、「馬出曲輪」(うまだしくるわ)にある長屋跡の「十五間多門」(じゅうごけんたもん)、「喰違虎口」(くいちがいこぐち)が配された「宇陀門」(うだもん)、用水池としても活用された水堀など、多彩な防御設備が見られます。
遺構が広域にわたっているため、見学の所要時間は約3時間。険しい道も多いので、訪れる際は動きやすい靴や服装がおすすめです。
| 施設名 | 高取城跡 |
|---|---|
| 所在地 | 〒635-0101 奈良県高市郡高取町大字高取 |
| 電話番号 | 0744-52-1150(高取町観光案内所) |
| 営業時間 | 散策自由 |
| 休業日 | 無休 |
| 料金 | 無料 |
| 交通アクセス | 近鉄吉野線「壺阪山駅」下車(約10分)「バス停壺阪寺前」下車 徒歩:約1時間 |

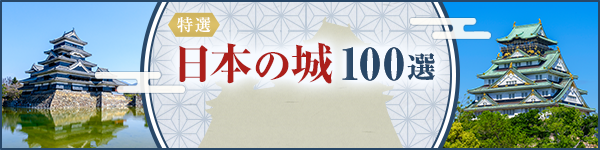
備中松山城

山城でありながら、唯一天守が現存しているのが、この備中松山城です。
城郭の縄張が4つの峰にまたがるという大規模な構造になっており、天守は標高約430mの「小松山」(こまつやま)に築かれています。
2層2階、長辺約14mと小規模ながら、日本一高所に現存する天守としても有名です。
築城の歴史は古く、最初に建てられたのは1240年(仁治元年)だと言われています。その後、地元で実質的に土地を支配していた国人領主(こくじんりょうしゅ)が次々とこの城を治め、戦国時代には「三村氏」(みむらし)の居城として発展。このころ、大規模な拡張工事が行われ、巨大山城へと変貌を遂げました。
その後、三村氏と「毛利氏」(もうりし)との間で起こった「備中兵乱」(びっちゅうへいらん)によって三村氏は滅亡。毛利氏の所領となったのちは、備中国(現在の岡山県西部)の要衝として重視され、江戸時代以降も「福山藩」(ふくやまはん:広島県福山市周辺)や「赤穂藩」(あこうはん:兵庫県赤穂市周辺)の支城となり、城番が置かれ続けました。
ちなみに「忠臣蔵」(ちゅうしんぐら)で有名な「大石良雄(内蔵助)」(おおいしよしお/くらのすけ)も、一時期城番を務めています。
なお、現在見られる近世城郭の姿へ改修されたのは、1683年(天和3年)ごろ。当時の城主「水谷勝宗」(みずのやかつむね)によって天守が建造されたと言われています。
明治時代の「廃城令」で備中松山城は商家に売却され、解体の危機を逃れました。しかし、あまりに険しい立地に広がっていたことから放置。一時は崩壊寸前まで荒廃が進んでしまいました。そこで救いの手を差し伸べたのが高梁市です。
昭和初期に修復を行い、現在は天守のほか、「二重櫓」(にじゅうやぐら)や「三の平櫓東土塀」(さんのひらやぐらひがしどべい)、さらにはひな壇状に並ぶ石垣群など、貴重な遺構が多数保存されています。
見学する場合は、ふもとから山頂の天守までは徒歩約1時間。見学も含めると約3時間あれば主要な遺構をひと通り巡ることができます。
なお、備中松山城は絶景スポットとしても有名。秋から春の早朝、気象条件が合えば雲海に浮かぶ幻想的な姿が見られます。近隣の山に設けられた「雲海展望台」(うんかいてんぼうだい)から望む「天空の城」も、備中松山城ならではの魅力なのです。
| 施設名 | 備中松山城 |
|---|---|
| 所在地 | 〒716-0004 岡山県高梁市内山下1 |
| 電話番号 | 0866-22-1487(高梁市松山城管理事務所) |
| 営業時間 | 【4~9月】9:00~17:30(入城:17:00まで) 【10~3月】9:00~16:30(入城:16:00まで) |
| 休業日 | 年末年始 |
| 料金 | 【入場料】 一般:500円、小・中学生:200円 |
| 交通アクセス | JR伯備線「備中高梁駅」下車 車:約10分(徒歩:約1時間30分) |